CP-ISRA 国際ボッチャ競技規則
CP-ISRA 国際ボッチャ競技規則 第10版 序文
ボッチャの競技の競技規則を、ここに規定した。
脳性まひ国際スポーツ・リクレーション連盟(CPI-SRA)ボッチャ委員会(CBC)が主催するすべての国際競技会にこのボッチャ競技規則を適用する。
これらの競技会には、カテゴリーA、BまたはCとして認可されたすべての種目で構成され、また地域の選手権大会を含め、世界選手権、ワールドカップまたパラリンピックが含まれる。
大会を開催する候補地として立候補する場合、大会が開催される年の18ケ月前までにCPI-SRAに加盟している加盟国の連盟がCBCに入札を行う。
大会を開催する国の連盟は競技規則を明確にするための解釈を加えることはできる。
しかし、本競技規則の意味を変えてはならない。
またそれらの解釈はCBCに提出する認可申請書に明確に記載する。
ボッチャ競技の精神
Cボッチャ競技の倫理と精神は、テニスの場合と同様である。つまり、多くの参加者がいることは歓迎されるし、かつ望ましい。しかし、選手がボールを投げる動作をしている間は、観客や団体戦のメンバーで競技を行っていない選手も含めて、静粛にすることが特に望まれる。
1.用語の定義
| 用 語 | 解 説 |
|---|---|
| ジャックボール | 標的になる白色のボール。 |
| ボール | 赤色または青色のボールのいずれか一方。 |
| サイド | 個人の部のボッチャでは、1名の選手を意味する。 また団体の部は名、ペアの部は2名の選手を1つの単位として意味する。 |
| コート | プレーする複数のボックスを含む境界線で囲まれたプレーをするエリアを指す。 |
| マッチ(対戦) | 2つのサイド間で規定の回数のエンドまで競技をすること。 |
| エンド | 1つの対戦で、2つのサイドがジャックボールとボールの全部を投げ終わったとき、1つの対戦のひと区切り(セクション)となる。 |
| アシスティブ・ディバイス(補助具) | BC3の選手が競技をするのを助けるために使う手段で、例えば、ランプやシュートを指す。 |
| バイオレーション(反則) | この競技規則に違反したと考えられる選手、サイド、サブスティチュート(交替要員)、スポーツ・アシスタントまたはコーチの行為を指す。 |
| スロー | 1つのボールをコート上に進ませることを意味する用語。 これには、投げる、蹴る、あるいはアシスティブ・ディバイス(補助具)を使って、ボールを放つことが含まれる。 |
| デッドボール | スローの後にコート外に出たボール、反則をしたため、レフリーがコートから取除いたボール、または一方のサイドの持ち時間が過ぎた後、投げられなかったボールを指す。 |
| ディスラプティッド・エンド(無効エンド) | 偶然にまたは故意に、複数のボールが正規のプレー順序でない順序で動かされた場合を指す。 |
| コート | プレーする複数のボックスを含む境界線で囲まれたプレーをするエリアを指す。 |
| Vライン | スローしたときにジャックボールが越えなければならないとされている線を指す。 |
| イエローカード | 固い紙かプラスティックでできた黄色のカード。 寸法は7×10cm。 レフリーは警告を出すためにこのカードを示す。 |
| レッドカード | 固い紙かプラスティックでできた赤色のカード。 寸法は7×10cm。 レフリーは失格させるためにこのカードを示す。 |
2.用具と設備
競技会を開始する前に用具の点検を行う。それは審判長または/あるいはTD(技術代表)が定めた時に、審判長から指名された人が行う。理想的にはプレーを始める48時間前に行う。
点検する用具は、ボール、車椅子、補助具(ランプス)、頭、腕または口につける補助具(ポインター)等である。
用具は競技会の間、審判長自身の判断でいつでも無作為に抜き打ち的に点検できる。この無作為の点検でボールが規定にもし合致していなければ、その選手または一方のサイドには10.4項に従って警告が発せられ、それらのボールを大会組織委員会がその競技会の最終日のエンドが終わるまで保管する。
またその警告はスコアシート(得点用紙)に記載され、その通知が招集所の入口に掲示される。
2.1 ボッチャボール
1組のボッチャボールは、赤色ボール6個、青色ボール6個、白色のジャクボール1個からなる。
認可を受けた競技会で使用されるボッチャボールは、CP-ISRAボッチャ委員会CBCが定めた基準に適合したものを使う。
| 2.1.1 | ボッチャボールの基準: 重量 : 275±12 g、 周長 : 270±8 mm ボールが上記の基準に合致しておれば、商標をボールに記載する必要はない。 |
| 2.1.2 | ボールの色は定められた色である赤、青、白とする。 ボールにはカットマークのような改変できることを示すような目で見える印がない良好な状態であること。 ボールにどんなスティッカーも貼ってはならない。 改変の形跡が認められるボールは使用を認めない。 |
2.2 メジャーリング・ディバイス(計測器具)
各認可を受けた種目の審判長/TDに対して、CBCが提供する。
2.3 スコアボード(得点表示板)
これをすべての選手が見える位置に置く。
2.4 タイミング・イクイップメント(計時用具)
できれば電子式のものとする。
2.5 デッドボール・コンテナー
そこにボールがいくつ入っているか、選手が見れるものとし、すべての選手が見える位置に置く。
2.6 赤色/青色のカラーインディケーター
どちらのサイドがプレーするのか、選手たちがはっきり分かるもので、卓球のラケット状のもの。
2.7 コート
| 2.7.1 | コートの表面はフローリング材を敷いた、または木製の体育館の床のように平坦で滑らかであること。 表面は汚れていないこと。 |
| 2.7.2 | 寸法は12.5m×6mとする。( コートの作り方を参照) |
| 2.7.3 | コートのマーキングは、すべて幅が2cmと5cmの間とし、目に付きやすいものとする。 ラインの表示をするために粘着テープを使用する。外側の境界線、スローイングライン、Vラインに、幅が4cmから5cmのテープを使用し、またスローイングボックスの区切線やクロス(十字のマーク)のような内側の線に幅が2cmのテープを使用する。 規定のクロス(十字線)の寸法: 長さが25cm, 幅が2cmのテープを使う。 |
| 2.7.4 | スローイングエリアを6つのスローイングボックスに区分する。 |
| 2.7.5 | スローイングラインとVラインの間のエリアに、もしジャックボールが落ちれば無効となる。 プレーが無効と見なされるエリアのサイドにVラインに使うテープを使用する。 |
| 2.7.6 | 中央に示した“ 十 ”のマークは、ジャックボールを置き直す位置であり、またタイブレークのエンドにおけるジャックボールを置く位置にもなる |
| 2.7.7 | コートの外側の線を計測する場合、測定はすべて対象となる線の内側(うちずら)を測る。 コートの内部の線は、そのマーキングのどちらかの側に一様に真っ直ぐ伸ばしたテープ上に記した細い鉛筆の線までを測定する。(コートの作り方を参照) |
3.出場資格
競技の出場資格は、CPI-SRA競技規則マニュアルのクラス分けの項に詳細に記載してある。
そのマニュアルには、選手のクラス分け、再度クラス分けする場合、および抗議の手順だけでなく、分類の仕方の詳細も記載してある。
4.競技の部
4.1 総則
競技には7つの部門があり、各部門とも男女どちらか一方の選手が競技する。
それらの部門は、
| 個人の部: | BC1クラス、BC2クラス、BC3クラス、BC4クラス |
| ペアの部: | BC3クラスに分類された選手のためのもの |
| ペアの部: | BC4クラスに分類された選手のためのもの |
| チームの部: | BC1とBC2に分類された選手のためのもの |
4.2 個人BC1の部
CP-ISRAのクラス分け制度で、CP1またはCP2(足でプレーする選手)に分類された選手たちが競技する。選手たちは1名のスポーツ・アシスタントに競技の補助をしてもらうことができる。
スポーツ・アシスタントは、指定されたプレイングボックスの背後に位置する。
これらのスポーツ・アシスタントは、以下の事を行う。 つまり、
* 選手の車椅子を調整あるいは安定させる。
* 選手にボールを1個渡す。
* ボールを丸める。
4.3 個人BC2の部
CP-ISRAのクラス分け制度で、CP2(U)に分類された選手たちがプレーする。
選手たちは、1名のスポーツ・アシスタントの補助を受けることができない。
選手たちは、自分の持ち時間内で、コートから落としたボールを拾い上げ、またはコートに入る助力をレフリーに頼むことだけができる。
4.4 個人BC3(補助具を使用する選手)の部
脳に起因、または脳に起因していなくても重度の運動機能障害を四肢のすべてに有する選手たちがプレーする。
選手たちは上手く車椅子を進めることができず、また助力を必要とするか、電動車椅子を必要とする。
選手たちはボールを持続してしっかりとつかむことができず、または放つ動作ができない。
選手たちは腕を動かせても、ボッチャのボールを安定してコートに進めるには上手く動かせる範囲が不十分である。各選手は、1名のスポーツ・アシスタントの補助を受けることができる。
そのスポーツ・アシスタントはその選手のボックスの中に入ったままとなるが、コートに背を向けたままとし、コート上のプレーを見ることはできない。(11.1.3/13.1項を参照)
4.5 個人BC4の部
脳に起因せず、または変性脳に起因して躯幹(くかん、つまり胴体)を動かせない障害を有し、重度の運動機能障害を四肢のすべてに有する選手たちがプレーする。
その選手はボッチャのボールを巧みに扱う十分な器用さがあり、ボッチャのボールを安定してコートに投げ入れることができる。
ボールの握りは不十分で、ボールを放すタイミングが上手くなく、腕の振りきりが不十分なこともあきらかである。
滑らかな動作や動きのスピードやタイミングを上手く合わせるコントロールが不十分なことも見受けられる。
4.6 ペアBC3の部
選手たちは個人のBC3の部でプレーできる資格を有すること。
1組のペアBC3には1名サブスティチュートを含むこと。 例外はCBCが決定し、その決定が最終である。
各選手は個人戦でプレーする競技規則で定められているように、1名のスポーツ・アシスタントの補助を受けることができる。
この区分におけるプレーの競技規則は、2番から5番のボックスが適切な順番で使われる以外は、団体の部での競技と同じである。
4.7 ペアBC4の部
選手たちは個人のBC4の部でプレーできる資格を有すること。
1組のペアBC4には1名のサブスティチュートを含むこと。 例外はCBCが決定し、その決定が最終である。 この区分におけるプレーに対する競技規則は、2番から5番のボックスが適切な順番で使われる以外は、団体の部での競技と同じである。
4.8 チーム(団体)の部
選手たちは個人のBC1の部またはBC2の部でプレーできる資格を有すること。
1組のチームには少なくとも1名のBC1の選手がコート上にいること。
各チームは1名のスポーツ・アシスタントの補助を受けることができる。
そのスポーツ・アシスタントは個人戦のBC1について定めた競技規則に従う。
各チームは3人の選手がコートに出て、マッチを始めなければならないし、1名か2名のサブスティチュートを入れておくこと。
4.9 コーチ
プレーの各部門に1名のコーチが、競技会毎に指定されたウォームアップ場とコールルーム(招集所)に入ることができる。
4.10
クラス分けの詳細については、CP-ISRAのマニュアルを記載してある。
5.対戦形式
5.1個人の部
個人の部ではタイブレークになった場合を除き、1つの対戦は4エンドで行なう。
各選手はジャックボールをコントロールしながら、選手の間で交替しながら2つのエンドを開始する。
各選手は6個のカラーボールを受取る。
赤色のボールを投げるサイドが3番のボックスに、青色のボールを投げるサイドが4番のボックスに入る。
コールルームに入るとき、各選手は6個の赤色のボールと6個の青色のボール、1個のジャックボールをコールルームに持ち込むことができる。
5.2ペアの部
ペアの部では、タイブレークになった場合を除き、1つのマッチは4エンドで行なう。
各選手は、スローイング・ボックスの2番から5番へ数字の順番にパスしながらジャックボールをコントロールして1つのエンドを開始する。各選手は3個のボールを受取る。
赤色のボールを投げるサイドが2番と4番のスローイング・ボックスに入り、青色のボールを投げるサイドが3番と5番のスローイング・ボックスに入る。
| 5.2.1 | ペアの部のボールの数 選手1名につき最大3個のボールとペア毎にジャックボールは1個。 1つ(または複数)のセットの残りのすべてのボール、およびサブスティチュートが使ったボールは指定されたエリアに収納する。 |
| 5.2.2 | コールルームに入るとき、ペアの部の各選手は3個の赤色のボールと3個の青色のボール、1個のジャックボールを持ち込むことができる。 |
5.3チームの部
チームの部ではタイブレークになった場合を除き、1つのマッチは6エンドで行なう。
各選手は、スローイング・ボックスの1番から6番まで数字の順番にパスしながらコントロールして1つのエンドを開始する。
各選手は2個のボールを受取る。赤色のボールを投げるサイドが1番、3番と5番のスローイング・ボックスに入り、青色の赤色のボールを投げるサイドが2番、4番と6番のスローイング・ボックスに入る。
| 5.3.1 | チームの部のボールの数 選手1名につき最大2個のボールと団体毎にジャクボールは1個。 1つ(または複数)のセットの残りのすべてのボール、およびサブスティチュート(交代要員)が使ったボールは指定されたエリアに収納する。 |
| 5.3.2 | コールルームに入るとき、団体の部の各選手(サブスティチュートを含む)は2個の赤色のボールと2個の青色のボールと団体毎に1個のジャックボールを持ち込むことができる。 |
6.プレー
1つの対戦の準備で、正式な手順はコールルームから始まる。
ゲームは第1エンドを始める時に、最初に投げる選手にジャックボールを渡して始まる。
6.1 競技開始時間
両方のサイドに競技の開始時間を知らせる。
プレーの区分で規定したように、または組織委員会の競技マニュアルに特別に記載されているように、選手たちはこの競技開始時間の15分前までにコールルームに来なければならない(19.1項を参照)。
公式時計を1個コールルームの外に設け、はっきりと分かるように表示する。
所定の時間になれば、コールルームは閉じられ、その他の人は誰も入れず、または用具もその出場の意思表示の後は入れることは認められない。
コールルームに自分のボールを持ち込むサイドは、そのマッチの間は自分のボールを使う。
(例外措置を審判長またはTDが考慮できる)
6.2 ボッチャボール
対戦の開始時間に現われないサイドは、そのマッチで競技する権利を失う。(10.4.6項を参照)
| 6.2.1 | 選手またはサイドは承認を受けた自分自身のボールを使うことができる。 個人の部で各選手は自分のジャックボールを使うことができる。 |
| 6.2.2 | 競技会の組織委員会は、この競技規則の2.1項の規定に合致した複数セットのボッチャボールを、もしできればコート毎に2セット準備する。 |
| 6.2.3 | コインストスの前後で、一方のサイドは、ジャックボールも含め、ボッチャボールを1つのマッチの前に点検できる。 |
6.3 コイントス
レフリーがコインを1枚はじいて、勝った方が赤色ボールか青色ボールでプレーするかを選択する。選手たちは指定されたボックスに入って位置決めをする。
6.4 ウォームアップボール
各サイドはレフリーから指示があったら、自分の複数のウォームアップボールを投げることができる。1名の選手/サイドは2分間以内に、6個までウォームアップボールを投げる事ができる。
彼らはジャックボールを投げることはできない。
サブシティチュートたちはどんなときもウォームアップボールを投げる事はできない。
6.5 ジャックボールの投球
| 6.5.1 | 赤色ボールを投げるサイドが、常に第1エンドを開始する。 |
| 6.5.2 | レフリーが、口頭でジャックボールを持ってくるように指示し、そのジャックボールを適切な選手に渡し、そのエンドの開始を知らせる。 |
| 6.5.3 | その選手は、ジャックボールをコートの有効なエリア内に投げ入れるようにする。 |
6.6 ファールとなるジャックボール
| 6.6.1 | 以下の場合、ジャックボールはファールとなる。つまり、 *ラインを越えなかった *Vラインを越えたが、その後で無効なエリアに戻った *コートの外側に投げた *ジャックボールを投げる選手が反則をした |
| 6.6.2 | もしそのジャックボールがファールになれば、その時は次のエンドでジャックボールを投げる順番になっている選手が投げる。もし最終エンドでジャックボールがファールになれば、第1エンドでジャックボールを投げた選手が投げる。ジャックボールがコート内に投げ入れられるまで、この順番で次々に投げ続ける。 |
| 6.6.3 | ジャックボールがファールになれば、その次のエンドで、ジャックボールをファールせず、ジャックボールを投げる順番になっていた選手が投げる。 |
6.7 コート内に最初のボールを投げる
| 6.7.1 | ジャックボールを投げる選手が、また最初のカラーボールも投げる。 |
| 6.7.2 | そのボールがコートの外側に投げられ、または反則でボールが除去されたなら、そのサイドはコート内の有効なエリア内にボールが着地するまで、またはそのサイドのボールが全部投げ終わるまで続ける。ペアの部やチームの部の場合、スローを指示されたサイドのどの選手も2番目のボールをコート内にスローできる。そのサイドのキャプテンがそれを決める。 |
6.8 相手側の最初の投球
| 6.8.1 | その後で、相手側のサイドが投げる。 |
| 6.8.2 | そのボールがコートの外側に投げられ、または反則でボールが除去されたなら、そのサイドはコート内の有効なエリア内にボールが着地するまで、またはそのサイドのボールを全部投げ終わるまで続ける。 ペアの部やチームの部の場合、キャプテンが指示したどの選手でも投げることができる。 |
6.9 残ったボールの投球
| 6.9.1 | 次に投げるサイドは、もし自分たちのボールをすべて投げてしまっていなければ、ジャックボールに最も近いボールになっていない方となる。 そしてその場合、もう一方のサイドが次に投げる。 |
| 6.9.2 | 前項に示した手順を両サイドがすべてのボールを投げ終わるまで続ける。 |
6.10 エンドの終了
各サイドに与えられたどんなペナルティーボールも含め、すべてのボールが投げられたら、レフリーがそのエンドの得点を付ける(7.項を参照)。その後で、レフリーは口頭でそのエンドが終了したことを宣言する。
コートからどんなボールも動かす前に、レフリーは、そのスポーツ・アシスタントがコートの方に振り向くことを認める。
もしBC3の部の選手の1名のスポーツア・シスタントが、どちらか一方に与えられたペナルティーボールも含めすべてのボールが投げられた後で振り向き、コートに入り、またはその選手と口を利いたりしたら、再度そんなことをしないように伝えられ、やさしい警告を受ける。
この後で、もし、そのスポーツ・アシスタントの選手/サイドがレフリーに計測を求めても、レフリーは計測をしない。
6.11 その後のエンドの準備
選手たちと彼らのスポーツ・アシスタントたち、または競技役員たちは次のエンドを始めるためにボールを回収する。その後で、その後のエンドが始まる。(6.5.2項を参照)
6.12 スロー(投球)
| 6.12.1 | レフリーが開始の合図をするか、またはカラーボールのどちらを投げるかを指示するまで、ジャックボールまたはカラーボールを投げてはならない。 |
| 6.12.2 | ボールを投げる瞬間に、その選手、選手たちのスポーツ・アシスタント、彼らの車椅子、またボックスの中に持ち込まれたどんな用具も、コートのマーキング、またはその選手のスローイングボックスと見なされないコートの表面のどの部分にも触れてはならない。 |
| 6.12.3 | ボールが放たれる時、その選手の少なくとも一方の臀部(でんぶ)はその車椅子のシートに接触していなければならない。 |
| 6.12.4 | ボールが放たれる時、そのボールはその選手のスローイングボックスの外側にあるコートのどの部分にも触れてはならない。 もしボールが投げられ、またその投げた選手または相手側の選手または彼らの用具に当たって跳ね返ったら、今尚プレー中であると見なされる。 プレー中のボールが何にも触れずに、勝手に転がればコート上のその転がった位置にボールを置いたままにする。 |
6.13 コートの外に出たボール
| 6.13.1 | ジャックボールも含め、どんなボールも、境界線に触れ、またはそれを越えたら、コートの外に出たと見なされる。 |
| 6.13.2 | 線に触れ、あるいは線を越えてから再びコートに入ったボールは、コートの外に出たと見なされる。 |
| 6.13.3 | 6.17項の場合を除き、投げてコートの中に入らなかったボールは、コートの外に出たと見なされる。 |
| 6.13.4 | コートの外に投げられたどんなボールもデッドボールとなり、デッドボール入れに収納される。これらの場合、レフリーが最終的な決定者である。 |
6.14 コートの外に押し出されたジャックボール
| 6.14.1 | その対戦中に、そのジャックボールがコートから押し出されたら、そのジャックボールは“置き直すジャッククロス"の位置に置き直される。 |
| 6.14.2 | 既にその置きなおし用の十字線上にボールが1個あるために、前項のようにすることができなければ、そのジャックボールをその十字線の正面にできる限り近づけ、両側のサイドラインの中央に位置するように置く。(“十字線の正面"とは正面のスローイングラインと置き直すジャッククロスとの間のエリアを意味する) |
| 6.14.3 | ジャックボールを置き直したら、6.9.1項に従い、次に投げるサイドが決定される。 |
| 6.14.4 | ジャックボールを置き直した後に、コート上にカラーボールが1つもなかったら、そのジャックボールを押し出した方のサイドがプレーする。(6.15項を参照) |
6.15 等しい距離にある複数のボール
次にどのサイドが投げるかを決めるに当たり、もし2個以上の異なったカラーボールがジャックボールから等距離にあり、ジャックボールにもっと近い別の複数のボールがなければ、最後に投げた方のサイドが再び投げる。その後で、投げるサイドは等距離でなくなるまで、または一方のサイドが自分自身のボールをすべて投げ終わるまで交互に行う。その後、プレーを通常通り続行する。
6.16 同時に投げられたボール
そのサイドが投げる順番のときに、同時に1個以上のボールを一方のサイドが投げたら、両方のボールがプレーされたと見なされ、コート上に残される。競技時間が少なくなってきたので、同時に1個以上のボールを投げて、優位に立とうとする意思があると、レフリーが判断すれば、そのとき投げた複数のボールは除去される。
6.17 落としたボール
もし選手がたまたまボールを落とし、その選手がアピールすれば、レフリーはそのボールでその選手が再度プレーすることを認めることができる。例えば、ボールを落としたのが、無意識な行為によるか、またはそのボールを投げるか、または進めるために故意にした行為かどうかの判断はレフリーによる。
1つのボールを再度投げることができる回数に制限はない。
そして、レフリーだけが決定できる。この場合、持ち時間を止めない。
6.18 レフェリーのミス
もしレフリーのミスで間違ったサイドが投球したら、そのボールまたは複数のボールはそれを投げた選手に戻される。この場合、持ち時間を点検し、適切に修正する。
どの複数のボールにでも混乱が生じたら、そのエンドはディストラプティド・エンド(混乱したエンド)として取り扱う。(12.項を参照)
6.19 サブスティチューション(選手交代)
ペアBC3とBC4の部で、各サイドは1名のサブスティチューションが一つのマッチ中に認められる。(4.6項を参照)
チームの部で、1つのマッチ中に2名のサブスティチューションが各サイドに認められる。
サブスティチューションはエンドとエンドの間で行ない、レフリーにサブスティチューションの選手を知らせる。サブスティチューションで、その対戦を遅らせてはならない。
一旦そのマッチから退いた選手たちは交代の選手としてマッチに戻ることはできない。(4.8項を参照)
6.20 交代する選手とコーチの位置
コーチたちと交代の選手たちは、適切に決められたコートの端部で待機する。
しかし、このエリアの定義は、組織委員会により定められ、コート全体の作り方による。
7.得点
| 7.1 | ペナルティーボールも含め、両サイドがすべてのボールを投げ終わった後で、もし適切であるならば、レフリーが得点を数える。 |
| 7.2 | ジャックボールに最も近いボールを有するサイドが、相手側のジャックボールに最も近いボールよりも、ジャックボールにより近ければ、それぞれのボールに対して、1点の得点を得る。 |
| 7.3 | 異なった色の2個以上のボールがジャックボールから等距離にあり、他の複数のボールがそれらよりももっと近くになければ、その時ボール1個につき1点が各サイドに与えられる。 |
| 7.4 | 各エンドが終了した時、レフリーはスコアシート上の得点と得点表示板が正しく表示されていることを確認する。 選手たち/キャプテンたちには得点が正しく記録されているのを確認する責任がある。 |
| 7.5 | 複数のエンドが終了した時、各エンドの得点を加算し、合計得点がより多い方のサイドが勝者として宣言される。 |
| 7.6 | もし計測をしなければならないか、1つのエンドが終わったときに、その判定が接近している場合、レフリーはキャプテンたち(または個人の部の選手たち)を呼び寄せることができる。 |
| 7.7 | 得点が同点なら、“タイブレーク”のエンドを行う。リーグ戦では、タイブレーク・エンドで得た得点は、そのゲームにおける選手の得点として考慮しない。タイブレークは単に勝者を決定するだけのものである。 |
8.タイブレーク
| 8.1 | “タイブレーク”とは、更に余分にもう1”エンド”競技を行なうことである。 |
| 8.2 | 選手全員は、自分たちが最初にいたボックスに留まる。 |
| 8.3 | タイブレーク・エンドでは、どちらのサイドが最初にプレーするかをコイントスで勝った方が選ぶ。 最初にプレーするそのサイドのジャックボールを使う。 |
| 8.4 | ジャクボールを“置き直すジャッククロス”の位置に置く。 |
| 8.5 | その後で、その“タイブレークエンド”を、通常の“エンド”と同じ様にプレーする。 |
| 8.6 | 7.3項に詳しく記載した事態が生じ、各サイドがこの“エンド”でも同点となれば、それらの得点を記録し、2回目の“タイブレーク”を行う。今度は相手側のサイドがその“エンド”を開始する。“最初の投球”を両サイド間で交互に行うこの手順を勝者が決まるまで続ける。 |
9.コート上における動き
| 9.1 | 次の投球準備で車椅子を操作するために、スローイング・ボックス・ラインを越える場合以外はプレーイング・ボックスから動く前に、常にレフリーの許可を求めなければならない。 | ||||
| 9.2 | 選手たちはその対戦中ずっと、指定された自分たちのスローイング・ボックス内に留まること。しかし、次の場合、ボックスから離れる許可をレフリーに求めることができる。 | ||||
|
|||||
| 9.3 | BC3の選手たちが次の投球準備をしているとき、またはランプの方向を決めている間は、他のボックスに入ることはできない。(9.1項を参照)もしこうした場合、レフリーは、その選手に彼らのランプの位置決めをする前の自分たちのボックスに戻るように指示する。 | ||||
| 9.4 | どの選手でもコートに行くために助力が必要なら、彼らはレフリーまたはラインズマンに助力を頼むことができる。 |
10.ペナルティー
10.1総則
反則をした場合、3種類のペナルティーがある。
即ち、
*ペナルティー
*リトラクション(取消し)
*警告と失格
10.2ペナルティー
| 10.2.1 | 1つのペナルティーとは、余分に2つのボールが相手サイドに与えることであり、そのエンドの終りに投げる。 | ||||
| 10.2.2 | ペナルティーボールを得た方のサイドの複数のデッドボールを使う。デッドボールが十分なければ、その時はジャックボールから最も遠いそのサイドのボールを使う。 | ||||
| 10.2.3 | “ペナルティーボール”にできるボールが複数個あれば、その時どのボールを使うかを、そのサイドが選択する。 | ||||
| 10.2.4 | もし得点圏にある複数のボールが、“複数のペナルティーボール”として使われる場合、レフリーはそれらのボールを取り去る前に、その得点を記録しておかなければならない。その“複数のペナルティーボール”を投げた後、追加の得点が得られれば、もとの得点に加える。もしそれらの複数のペナルティーボールを投げる行為において、相手側の1つのボールがジャクボールにより近くなるように、1人の選手は複数のボールの位置を変えなければならない。その後、レフリーはその新しい位置からそのエンドの得点を記録する。 | ||||
| 10.2.5 | 一方のサイドが、1つのエンドで複数の反則をした場合、各反則で与えられる2個の“ペナルティーボール”を別々に投げる。従って2個の“ペナルティーボール”(第1回目の反則に対する)は回収され、その後でプレーされ、その後で2個の“ペナルティーボール”(第2回目の反則に対する)は回収され、その後でプレーされ、以下同様とする。 | ||||
| 10.2.6 | 両サイドがした反則は相殺する。例えば、1つの“エンド”中に赤色ボールのサイドが2つ反則をし、青色ボールのサイドが1つだけ反則した場合、その時、青色ボールのサイドは1つ分の反則だけに対して、“ペナルティーボール”を得る。 | ||||
| 10.2.7 | “ペナルティーボール”が与えられるような反則が、“ペナルティーボール”を投げている間に起こったら、レフリーは以下の順番で、 | ||||
|
10.3リトラクション(取消し)
| 10.3.1 | リトラクションとは、1つのバイオレーションがあった時、投げられた1個のボールをコートから取除くことも含まれる。そのボールはデッドボール・コンテナーに収納する。 |
| 10.3.2 | 投げる行為中に反則が生じた場合だけ、1つのバイオレーションに対して、1つのリトラクションのペナルティーが与えることができる。 |
| 10.3.3 | リトラクションに結びつくような1つのバイオレーションが生じたら、レフリーはそのボールが他のボールを押しのける前に、そのボールを止めるように常に努める。 |
| 10.3.4 | もしそのボールが他のボールを押しのける前に、レフリーが止めるのに失敗したら、そのエンドは、ディスラプティッド・エンドと見なす。(12.項を参照) |
| 10.3.5 | 1つのリトラクションになるような1つのバイオレーションは、そのボールが放たれた時点に生じたものと見なす。 |
10.4警告と失格
| 10.4.1 | 1人の選手に警告を与えたら(黄色のカードを示して)、レフリーは得点票にそのことを記入する。 |
| 10.4.2 | 2回目の警告を受けたら(黄色のカードを示し、その後で赤色のカードを示して)、その選手は失格となる。(10.4.6項を参照) |
| 10.4.3 | もし1名の選手がスポーツマンらしくない振る舞いで失格になれば、レフリーは赤色のカードを示し、そのことを得点票に記載する。 |
| 10.4.4 | 個人の部またはペアの部で、1名の選手が失格になれば、そのサイドはその対戦で負けとなる。(10.4.8項を参照) |
| 10.4.5 | 団体の部で1名の選手が失格になれば、その対戦は残りの2人の選手で続ける。 失格になった選手が投げていないどのボールもデッドボール・コンテナーに収納される。あとの残りのどのエンドも、そのサイドは4個のボールで競技を続ける。 キャプテンが失格になれば、チームのもう1名のメンバーがその役目を果たすと見なす。 1つのチームで2番目の選手が失格になれば、そのサイドはその対戦の権利を失う。(10.4.8項を参照) |
| 10.4.6 | 失格になった選手は、同じ競技会でその後の対戦には復帰できる。 |
| 10.4.7 | 1人の選手がスポーツマンにふさわしくない振る舞いで失格になった場合、審判長とその対戦に関与していない、またはその選手と同じ出身国でない2名の国際審判員で構成される委員会で、その選手がその後の対戦に復帰できるかどうかを決定する。(10.4.9項を参照) |
| 10.4.8 | 一方のサイドが1つの対戦で権利を失ったら、その時、その相手サイドがもし6点を越える得点を取っていなければ、その対戦に対して6-0の得点が相手サイドに与えられ、6点を越える得点を取っておればその得点となる。失格した方のサイドの得点は0となる。 |
| 10.4.9 | 失格が繰り返された場合、組織委員会は、任命されたTDと協議の上、やむなく適切な制裁を考慮せざるを得なくなる。 |
11.バイオレーション(反則)
| 11.1 | 以下の場合は複数のペナルティーボールを与える対象となる。(10.2項を参照) つまり、 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11.2 | 以下の場合、複数のペナルティーボールが与えられ、投げたボールは撤去される。(10.2/10.3項を参照) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11.3 | 以下の行為をすればペナルティーボールが与えられ、警告―黄色のカードが提示される。 (10.2/10.4項を参照) |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11.4 | 以下の行為をすれば、投げたボールは取消しとなる。(10.3項を参照) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11.5 | 以下の場合、そのサイドに警告―黄色のカードが提示される。(10.4項を参照) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11.6 | 選手が審判員または相手側の選手たちにスポーツマンにあるまじき行為をした場合、失格―レッドカードの対象となる。(10.4項を参照) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11.7 | ジャックボールを投げる時に反則すれば、そのジャックボールはファールになる。(6.6項を参照)。 |
12.ディスラプティッド・エンド(混乱を生じたエンド)
| 12.1 | レフリーのミスや行為によって、1つのエンドが混乱した場合、レフリーはラインズマンと協議して、混乱させた複数のボールを混乱する前の位置に戻す(たとえそれらのボールが前の正確な位置になくても、レフリーは常にその前の得点を妨げないように努める)。 レフリーの考えでそれが出来そうにないと判断したら、そのエンドはやり直しをする。レフリーが最終決定をする。 |
| 12.2 | 一方のサイドのエラーや行為で1つのエンドが混乱したエンドになれば、レフリーは12.1項に従って処置するが、不公平な決定をしないように、不利益を受けたサイドと協議できる。 |
| 12.3 | もし混乱したエンドが引き起こされ、複数のペナルティーボールが与えられると、それらのペナルティーボールはその試合の再試合するエンドでプレーされる。もしその混乱したエンドを引き起こした選手またはサイドにペナルティーボールが与えられていれば、彼らはそれらのボールでプレーできない。 |
13.コミュニケーション
| 13.1 | 1つのエンド中に、選手、スポーツ・アシスタント、コーチとサブスティチュートたちとの間で、コミュニケーションを取ってはならない。 複数の例外は、 選手が自分のスポーツ・アシスタントに車椅子の位置を変えてもらい、アシスティブ・ディバイスを移動させ、ボールを丸めてもらい、またはボールを渡してもらうなどの特定の行為をやってもらうように頼む時。 コーチたちはスローの後やエンドの間で、選手をほめ、または激励するのはよい。 |
| 13.2 | ペアの部やチームの部で、1つのエンドの競技中に、レフリーから自分たちがスローする番であるとの指示がなければ、味方サイドのその他の選手たちと、選手たちは話ができない。 |
| 13.3 | エンドとエンドの間に、選手たちは選手同士、彼らのスポーツ・アシスタントおよび彼らのコーチたちと話ができる。一旦レフリーがそのエンドを始める用意をしたら、話を止めなければならない。 レフリーは長たらしい論争を許して、競技を遅らせない。選手交代をするのでなければ、タイムアウトの間、またはレフリーの許可がなければ、キャプテン/選手はエンドとエンドの間に自分のボックスを離れることはできない。(6.19/13.4項を参照) |
| 13.4 | チームの部またはペアの部の対戦では、1回のタイムがサイド毎に認められる。これはコーチまたはチームの部のキャプテンのどちらかが、エンドの間に求めることができる。タイムの時間は2分間である。 タイムの時、選手たちは自分たちボックスを離れても良いが、同じスローイング・ボックスに戻らなければならない。 タイムの間、選手たちはレフリーの許可がなければ、コートエリアを離れることができない。 もし何らかの理由で彼らがコートエリアを離れたら、彼らには警告(イエローカード)がなされ、それはスコアシートに記載される。(11.5.3項を参照) |
| 13.5 | 投げるのに邪魔になるような位置に、もう1人の選手が位置している場合、スローする選手はその選手に移動するように求める事ができるが、そのボックスから出るようには求められない。 |
| 13.6 | キャプテンだけでなく、どの選手もそのレフリーに、自分たちの持ち時間の中で話しかけることができる。 |
14.時間
| 14.1 | 各エンドの競技をするために、各サイドに持ち時間があり、タイムキーパーが計時する。 | |||||
| 14.2 | ジャックボールを進める時間は、一方のサイドに割り当てられた持ち時間の内には含まない。 | |||||
| 14.3 | 一方のサイドの持ち時間は、どちらのサイドが競技するかを、レフリーが指示した時点から始まる。 | |||||
| 14.4 | 一方のサイドの持ち時間は、投げた各ボールがコートの境界線内で静止するか、またはコートの境界線を横切った瞬間に時計を止める。 | |||||
| 14.5 | 持ち時間に達した時、一方のサイドのボールが投げられていなければ、そのボールとそのサイドの残りのボールは無効となり、デッドボール・コンテナー収納される。 BC3の部の選手たちの場合、ボールがランプを転がり始めたら、そのボールは放たれたと見なす。 |
|||||
| 14.6 | 持ち時間に達した後、一方のサイドがボールを投げたら、その後でレフリーはそのボールを止め、それがプレーを混乱させる前にコートから取り除く。 もしそのボールがその他のどれかのボールを混乱させれば、そのエンドはディスラプティッド・エンド(混乱したエンド)となる。 |
|||||
| 14.7 | ペナルティーボールには持ち時間の規定を適用しない。 | |||||
| 14.8 | 各エンドの間、両サイドの残り時間を得点表示板に表示する。各エンドが終わった時に、両サイドが費やした時間をスコアシートに記載する。 | |||||
| 14.9 | 1つのエンドをプレーしている間に、もし持ち時間が不正確に算定されたら、そのレフリーはその間違いを補償するため時間調整ができる。 | |||||
| 14.10 | 論争または混乱が生じている間、レフェリーは時計を止めることができる。通訳をするために1つのエンド中に止める必要があれば時計を止める。(15.10項を参照)もし可能ならば、その通訳はその選手と同じチームでないようにする。 | |||||
| 14.11 | 持ち時間は以下のとおりである。 | |||||
| 14.11 | 持ち時間は以下のとおりである。 即ち、 |
|||||
|
||||||
| 14.12 | タイムキーパーは残り時間が1分、30秒、10秒そして持ち時間一杯になった時、大きな声で明瞭に告げる。 | |||||
| 14.13 | タイムは2分間である。 |
15.アシスティブ・ディバイスの基準と規則
| 15.1 | アシスティブ・ディバイスは、横に倒した時に、2.5m×1mのエリア内に収まるような寸法でなければならない。ランプは付属品、延長部およびベースも含めて、計測する時は最大限に伸ばした状態で行う。 |
| 15.2 | アシスティブ・ディバイスにはボールの推進を助け、または加速し、減速させ、ランプの方向を定めるようなもの(たとえばレーザー、水準器、ブレーキ、照準器、望遠鏡等))を付けてはならない。一旦ボールがその選手から放たれたら、どんな方法によっても、どんなものでもボールの進行を妨害してはならない。 |
| 15.3 | 選手はボールをコートに放つ直前に、ボールを直接体に接触させる。体への直接の接触には選手の頭、腕または口に直接付けたアシスティブ・ディバイスが含まれる。この場合のアシスティブ・ディバイスの最大長さは50cmとする。もし選手の頭または口にそれがつけてあれば、額または口から計測する。 もし、選手の前腕に取り付けてあれば、肩の付け根から計測する。 スポーツ・アシスタントと選手がそのボールを同期させて放つことは認めない。 もし、こうしたら、そのボールは取り消しとなる。 |
| 15.4 | 複数の投球の間、アシスティブ・ディバイス(ランプ)をはっきりと右や左に移動させる。 もしランプがベースに固定されていて、独立してベースから移動できなければ、ランプ全体を右や左に移動させる。 |
| 15.5 | 選手は1つの対戦中に複数のアシスティブ・ディバイスを使用できる。レフリーが投げる番だと指示した後でのみ、選手はアシスティブ・ディバイスの変更ができる。すべてのアシスティブ・ディバイスはその選手のボックスの中に置いておく(11.2.1項を参照)。 |
| 15.6 | 各エンドの間、レフリー/ラインズマンは、スポーツ・アシスタントがプレーしているエリア内に顔を向けないように、アシスティブ・ディバイスを付けた選手たちのためにボールを回収する。 |
| 15.7 | ボールが放たれる時、アシスティブ・ディバイスはスローイングラインより前面に張り出してはならない。 |
| 15.8 | 個人の部で、1つのエンド中にランプが壊れたら、持ち時間を止め、選手はそのランプを修理するために10分間の時間を与えられる。ペアの部では、その選手のチームメートが使っているランプを共用できる。 ランプの取替えはエンドとエンドの間で行うことができる(取り替えた場合は審判長に連絡する)。 |
16.
| 16.1 | 1つの対戦中に、レフリーがその対戦の結果に影響するような一つの出来事を見逃し、または不正確な決定をしたと一方のサイドが感じることが有り得る。 その時、そのサイドの選手/キャプテンはこの状況に対して、レフリーの注意を引き、説明を求めることができ、持ち時間を止める(15.10項を参照)。 |
||||
| 16.2 | マッチの間、選手/キャプテンは審判長から裁定を求めることができ、審判長の決定が最終である。 | ||||
|
|||||
| 16.3 | 各ゲームの終わりに、競技した両サイドはスコアシートに署名を求められる。もし一方のサイドが、決定またはそのゲーム中の行為に対して、抗議したいと考える場合、またはレフリーがそのゲーム中に競技規則に従って行動していないと感じるならば、スコアシートに署名してはならない。 | ||||
| 16.4 | レフリーはスコアシートに結果を記録した後、競技終了の時間を記載する。 そのゲームが終了して30分間以内に、正式な抗議をしなければならない。 もし書面による抗議が受理されなければ、対戦結果は有効となる。 |
||||
| 16.5 | 必要事項を記入した抗議書の書式を選手/キャプテンまたはチーム・マネージャーが150ユーロ(約17000円)を添えて、大会事務局に提出する。この抗議書には、抗議するためにその時の状況、抗議を正当化するもの、引用する規則の条文の詳細を記載する。審判長または彼らが指名した者はできるだけ早く抗議委員会を開催する。 この抗議委員会は以下の者で構成される。 つまり、 *審判長 *そのゲームに関与していない、またはその抗議に関与する国の出身でない2名の国際審判員 |
||||
|
|||||
| 16.6 | もし抗議委員会の決定にアピールする必要があれば、更に詳細を記入した抗議書を受理した後に行われる。もしできるならば、これに関与する両者に聴聞を行う。 この抗議を受け次第、技術代表、または技術代表が指名した者はできるだけ早く以下のメンバーで構成される上訴委員会を開く。 つまり、 *指名されたTD *前回の抗議に関与しなかった、またはその抗議に関連しない国の出身であるもう2名の国際審判員 |
||||
|
|||||
| 16.7 | 抗議の対象となったゲームに関与するどちらかの側は、抗議委員会の決定の見直しを求めることができる。 彼らは抗議書に150ユーロを添えて、提出する。その抗議書は抗議委員会の元の決定を受け取ったときから30分以内に提出する。抗議委員会、またはそれが指名した者は、その選手またはサイド、あるいは適切な人(つまり、チーム・マネージャーまたはコーチ)が元の決定を受け取った時間を記録し、その書式に署名をする。 抗議に関するすべての審議は部外秘とされる。 |
||||
| 16.8 | もし抗議の決定の結果、再試合が必要になった場合、その抗議が生じるような状況となったそのエンドの初めから再試合をする。 | ||||
| 16.9 | 1つの対戦が始まる前に、もし1つの抗議に対する理由が分かっていると、その対戦が始まる前にその抗議を提出する。審判長、TDに抗議が出されることを知らせる。この規則に定められている手順にそのサイドが従わなければ、その抗議は検討の対象とならない。 |
17.車椅子
| 17.1 | 競技用の車椅子は、できるだけ標準的なものとする。しかし、日常生活のために加えた変更は、競技会での使用を認める。スクーターもまた使用できる。 |
| 17.2 | クッションまたは支持板を含めたシートの最高の高さは、床から太ももまたは尻がそのクッションに接触している場合、その最高点までが66cmである。 |
| 17.3 | 論争が生じた場合、審判長は指名されたTDと協力して、決定を行う。どんな決定が行われても、それが最終決定である。 |
18.キャプテンの責務
| 18.1 | ペアの部とチームの部では、各サイドをキャプテンが率いる。誰がキャプテンかレフリーに分かるようにはっきり明示する。キャプテンはチームの代表として行動し、以下の責任を負う。 つまり、 |
||||||||||||||||||
|
19.ウォームアップの手順
| 19.1 | 各対戦が始まる前に、指定されたウォームアップ・エリアでウォームアップできる。ウォームアップ・エリアは、組織委員会が各対戦のために指定した時間の前にプレーする選手たちが独占的に使用する。 選手たち、コーチたち、スポーツ・アシスタントたち(および各国毎に1名の通訳)はウォームアップ・エリアに入り、指定されたウォームアップ・コートに彼らの予定された時間内に向かうことができる。 |
|||||||
| 19.2 | 選手たちはウォームアップ・エリアに、以下に規定した最大人数の人と一緒に入ることができる。 つまり、 |
|||||||
|
||||||||
| 19.3 | もし必要ならば、国毎に1名の通訳はこのウォームアップ・エリアに入ることが出来る。 |
20.コールルーム
| 20.1 | 公式の時計を1個そのコールルームの外に設け、はっきりわかるように示しておく。 | ||||||||||||
| 20.2 | コールルームに入る前に、各選手は自分のナンバーとアクレカードがはっきり見えるようにしておく。 そのようにしなければ、コールルームに入ることを拒否される。 |
||||||||||||
| 20.3 | コールルームで出場の意思表示をする。すべての選手はそれぞれのゲームで予定された競技開始時間の15分から30分前の間に出場の意思表示をすること。 | ||||||||||||
| 20.4 | もしその選手がそのコールルーム・エリアの境界内にいれば、コーチは個人の選手の出場の意思表示をできるだけである。すべてのサイドはコールルーム内、および彼らの対戦を行う指定されたコートのエリア内にいること。 | ||||||||||||
| 20.5 | もし大会組織委員会側に起因する遅れがあれば、規則6.1項は適用しない。 もし何らかの理由で遅れれば、大会組織委員会はできるだけ早く、すべてのチームの監督に書面で連絡する。 |
||||||||||||
| 20.6 | 指定の時間にコールルームの戸は閉じられ、出場の意思表示の後、その他の人または用具をコールルームに入れることはできない(例外措置を審判長および/またはTDが考慮できる)。 | ||||||||||||
| 20.7 | もしレフリーに要請されれば、通訳たちはコールルームに入ることだけが出来る。 | ||||||||||||
| 20.8 | 選手たちはウォームアップ・エリアに、以下に規定した最大人数の人と一緒に入ることができる。 つまり、 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 20.9 | レフリーたちは所定の競技開始時間の15分前にその対戦を準備するためにコールルームに入る。 | ||||||||||||
| 20.10 | 選手たちは自分たちのナンバーとアクレカードの提示をレフェリーに求められる。 それにより、レフリーたちは選手たちの情報を確認できる。 |
||||||||||||
| 20.11 | コールルーム内で一旦出場の意思表示を済ませたら、選手たち、コーチたち、またスポーツ・アシスタンスたちはコールルームから離れてはならない。もし彼らが離れたら、コールルームには再度入ることができず、その対戦にもう参加することはできない。(例外措置はその審判長および/またはTDが考慮できる) | ||||||||||||
| 20.12 | すべてのスポーツ用具の点検とコイントス(6.3項参照)は、コールルームで行うことができる。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 20.13 | 招集所に持ち込んで良いボールの数 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
21.特別な状況
| 21.1 | 1つのエンドで中にもし選手が病気になれば(重大な状況)、その選手が介護を受けられるように、そのマッチを最大10分間中断することが出来る。持ち時間は停止される。 |
| 21.2 | 個人の部で、もし選手がプレーを続けることができなければ、マッチは没収となる(10.4.7項を参照)。 |
| 21.3 | ペアBC3の部で、10分間の介護の制限時間中にスポーツ・アシスタントたちはコートエリアの方を見ることはできない。選手は医療関係者から手当を受けなければならず、もし必要ならば、医療関係者はその選手のスポーツ・アシスタントに意思疎通を助けてもらうことができる。 |
| 21.4 | チームの部で、もし1名の選手がプレーを続けることができないならば、現在のエンドはその選手の残りの(複数の)ボールを投げずに終了させる。1名のサブスティチュートだけがエンド間にそのゲームに加わることができる。 (6.19項と10.4.5項を参照)もし1名の選手がジャックボールを投げる次の人であったが失格となり、または病気になってプレーを続けることができなければ、そのジャックボールはその次のエンドで投げることになっていた選手が投げる。 |
| 21.5 | ペアの部の競技で、もし1名の選手がプレーを続けることができないならば、現在のエンドはその選手の残りの(複数の)ボールを投げずに終了させる。もし彼らのチームメートが投げることのできる複数のボールを持っていたら、彼らの持ち時間でそれらのボールを投げることができる。1名のサブスティチュートだけがエンド間にそのゲームに加わることができる。(6.19項と10.4.5項を参照) 1名の選手はエンド間にそのゲームに加わらなければならない。(10.4.6項を参照) |
| 21.6 | ペアの部で、もし1名のスポーツ・アシスタントに医療上の問題があれば、その選手はそのエンドの残りを1名のスポーツ・アシスタントで兼任してもらうことができる。スポーツ・アシスタントたちの交替はエンド間で行う。 |
このマニュアルに記載していないような種類の状況が発生するかも知れないことをCBCは予測している。
それらの状況が発生した時は、そのTDおよび/または審判長が相談して対処する。
以下のページ(付録1,2,3)には、レフェリーたちの使うジェスチャー、抗議の手順の説明、およびコートの図面が示してある。
これらのジェスチャーはレフリーたちと選手たちが所定の状態を理解できるように開発されたものである。
レフリーがある特定のジェスチャーをするのを忘れても、抗議はできない。
競技規則 附録
審判員の公式なジェスチャー・合図
| 合図を送るべき状況 | ジェスチャーの内容 | 審判員が行うジェスチャー |
|---|---|---|
| ジャックボールまたはウォームアップボールを投げる指示 (規則: 6.4; 6.5) |
投球を指示するために手を動かす | 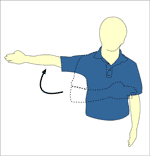 |
| カラーボールを投げる指示 (規則: 6.7; 6.8; 6.9) |
プレーするサイドのカラー板を示す | 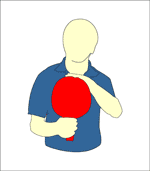 |
| タイム (規則: 13.4) |
手のひらを水平にして下に向け、他方の手の指を真っ直ぐ垂直に伸ばしてTの字を作り、どちらのサイドが求めたかを言う。(例:〜選手、チーム、国、ボールの色のタイムと言う) | 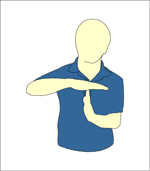 |
| 選手交代 (規則: 6.19) |
一方の前腕を他方の前腕の周りで回転させる | 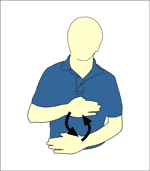 |
| 計測 (規則: 6.19) |
片手をもう一方の手に並べて、巻尺を使うように両手を動かす | 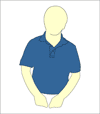
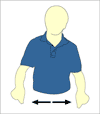 |
| キャプテンまたは個人の部の選手にコートに来たいか聞く (規則: 7.6) |
複数の人を指差し、次いで審判員の目を指差す | 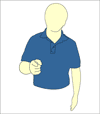
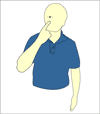 |
| 不適切なコミュニケーション (規則:11.1.3;13) |
口を指差し、もう一方の手の人差し指を横方向に動かす | 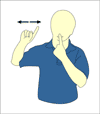
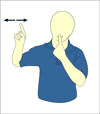 |
| デッドボール/コートの外に出たボール (規則: 6.13) |
ボールを指差し、前腕を垂直にあげて手を開き、手の平を審判員の方に向けて、アウトまたはデッドボールと言い、そして出たそのボールを高く上げる | 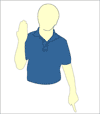
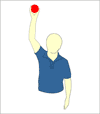 |
| 取消 (規則: 10.3; 11.2; 11.4) |
そのボールを指差し、そのボールをつまみ上げる前にその手の前腕の手を凹面にして上げる(可能ならばいつでも) |  |
| 2個のペナルティーボール (規則: 10.2; 11.1; 11.2; 11.3) |
2本の指を離して上げる | 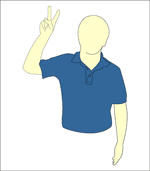 |
| 警告 (規則: 10.4; 11.3) |
違反を警告するためにイエローカードを示す | 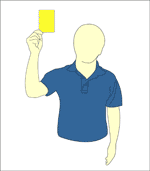 |
| 2回目の警告とその結果としての失格 (規則: 10.4. ) |
イエローカードを示し、次いでレッドカードを示す | 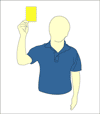
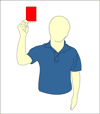 |
| 失格 (規則: 10.4; 11.6) |
レッドカードを示す | 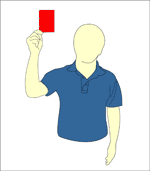 |
| 相殺する違反 (規則: 10.2.6) |
両方の親指を真っ直ぐに上に上げる | 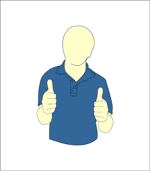 |
| エンドの終了 / 対戦の終わり (規則: 6.10) |
伸ばした両腕を交差させ、次いで広げる | 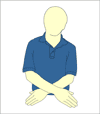
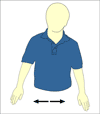 |
| 得点 (規則: 7) |
得点を示すために対応するカラー指示板の上に指を乗せる(例. 赤に3点) | 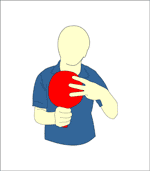 |
得点の表示例
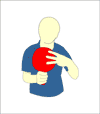 |
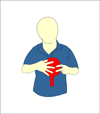 |
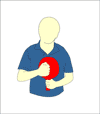 |
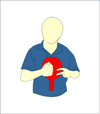 |
| 赤に3点 | 赤に7点 | 赤に10点 | 赤に12点 |
|---|
線審の公式なジェスチャー /合図
| 合図を送るべき状況 | ジェスチャーの内容 | 線審が行うジェスチャー |
|---|---|---|
| 審判員の注意を喚起する | 腕を高く上げる | 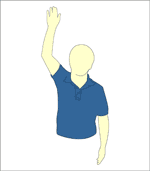 |
グラフィック・デザイナー:フランシスカ・ソトマヨル